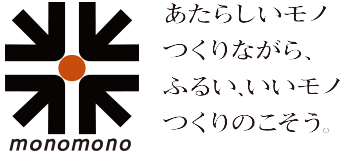「何もない中から一つでもいいことを探そうという発想が僕らの地域デザインの手法です」
自分で改良、デザインした木工ろくろをかついで、出稼ぎの村に入って、常駐、工芸の村に蘇らせた。以来、各地を実践指導してきたクラフトマン。いわば、時松辰夫氏は、山村クラフト伝導師。その活動はまだまだ続く。
工芸品は飾りでなく使って楽しい生活用具
―なぜ“山村クラフト”の世界に?
「山村クラフトというのは秋岡芳夫さん(工業デザイナー・故人)」がつけてくれた名前なんです。熊本県の事業のときですから平成3年、まだ比較的新しい。秋岡さんに仕事が行くんですよ。秋岡さんが私に手伝えと言ってきて。まあ、秋岡さんが虹を描いてくれて、その虹を消さないようにするのが、私の役割ですね。
クラフトという言葉は昭和30年代から使われていました。工芸が文展とか日展とかそういう権威あるところに行ってしまった。工芸って本来そんなものではない。日常の生活用具に取り戻そうという運動がクラフト運動だったんです。
私は学校へ行ったわけじゃないし、デザイナーでもないし、農家の三男坊です。ですからどうしても土に根付いた発想をしたくなるのね。まあ、そこのところが林業・山村との接点なんでしょうね。クラフトマンなんだけど林業寄りになっているのはなぜかというと、自分の生家が農家であって、そこと心情的に縁がきれていないからでしょう。
そして、秋岡さんは有名な工業デザイナーですが、氏との出会いの中で、それぞれの役割を持っていったのが地域振興というところに結ばれたんですね」
―秋岡さんと出会われたのはいつ頃?
「私の21歳のときで、ちょうど40年前。秋岡さんは当時すでに、町村の地場産業の振興のためのデザイン講習会をやっていました。大分県でも年1回、秋岡さんを呼んで、デザインの勉強会をした。その講習会で初めて出会ったんです」
―もうその頃、工芸で生きて行こうと決めていらしたのですか。
「私の一番やりたかったことは農業だけども、兄貴がいますし、二人でするほどの土地はないから、二番目に好きな指物大工になろうと思ってました。職業補導所の木工科を出て、福岡県大川市のタンス屋に弟子入り、4年の後、大分県立の日田工芸指導所(現、大分県日田産業工芸試験所)へ丁稚(研究生)に入ったんです。そこの木工部門に一人だけろくろをひいていた先輩がいて、1年間習いました。先輩は1年したら転職。指導所には私一人が残されて、ろくろを22年間担当し、日田の工芸振興に携わってきました。昭和55年に日田を辞めて、仙台に行くことにした。当時、秋岡さんは東北工業大学の工芸意匠科の学科長だった。おまえ来るなら手伝えということになって」
―では、秋岡さんに呼ばれて大野村へ行ったのではなかったのですね。
「そう。本当は若い頃学んだ東北の工芸をもう一辺勉強し直したかったのですが、来るなら1年でもいいから手伝えと。秋岡さんが1年というなら、3年ぐらいかかるだろうなと思いましたけれど。それではじまったのが大野村ですね。
秋岡教授は東北農山村のコミュニティ機能再生のための「裏作工芸」の実践的研究チームを学内に結成し、54年にすでに大野村計画を提案していた。けれど、講演会だけだから、村の人もわからんわね。わからんからというので秋岡さんは『一人一芸の村』という本を書いた。私が行った時もうその本はできていました。
提案段階だったものが、私が現地に入ったとき、村は計画受入れを決断し、実質出発したんです。大野村に行くとき、ろくろの機械をデザインして、日田で作ってもらって、かついで行きました」

出稼ぎ村が工芸の村に生まれ変わる
―それから本格的に地域振興に関わることになったんですね。
「昭和55年というのは、ちょうど地域振興という言葉が叫ばれ始めた時期ですよね。大分県では平松知事が一村一品を提唱した時。私はそれと入れ替わりに大分を出たことになりますが。秋岡さんとの関係は、21歳のとき知りあってから59歳まで(秋岡さんは1997年4月に亡くなられた)、ずっとつかず離れず。ですから、秋岡さんのモノ・モノ運動等の地域デザイン指導にはずっと関わってきたのです。
大野村で10年かけて、一応成功したと皆さんが言ってくれるの。大野村方式という実践例を作った、その過程ですが、当時、大野村というのは、貧しいところの象徴みたいに言われていた。岩手県の中でも一番貧しく、日本のチベットだとか言われていた、出稼ぎ村でした。
今の時代ですから、食べるものも情報も差はないから、出稼ぎに行ける人はいいけど、出稼ぎに行けない人はどうするかってことですよ。行けない人も行った人以上に楽しめる村の生活があってもいいんじゃないかという提案で始まった。大野村方式のすすめ方というのは、村が寂れて何もないというときにね、そんな中から何かいいことを村民一人一人が一つずつ探してみようという発想。それが僕らの地域デザインの手法です。
まず何が悪いのか現在を見直してみようと、全産業について、つぶさに調査する。木材については、今まで、家を建てるか、炭を焼くかしか考えられなかったけど、生活用具を作ると違う展開があるよ。そこのところは俺が受け持とうと。それがこの計画の中の私の分担なんです。私は林業は自分の担当と思って、熱心に通ったわね。唯一技術を持っていたのは私だけだし、それに私はフリーだから、大野村に住みついて教えたわけね。木材の生活用具への活用というテーマでは僕が常駐したから掛けた時間が他のものに比べて長い。そのため、その部分だけ突出した。それで工芸の村になってしまった。本当は、あらゆる産業を見直して、1人が一つずつテーマを持つ、一人一芸を目指していた。
炭にしかならんと言うのを、そうではないよ、この1mが80円の木を、俺だったら3万円にしてみせるよと。どうだやってみないかと投げかけてみたら、7人が、そんなうまい話ならやってみたいという。その7人が最後までつづいたわね。その過程で学校給食器が生まれ、マスコミに取り上げられたりしたこともあって勢いづき、工芸の一点を突破して全面展開。今では温泉やホテルもできて20万人も来てくれるまでになった。
それでぜひうちの村にも大野村の手法を教えて欲しいと言ったのが津山なのね。次が置戸、帯広、宮城県周辺の町村、匹見と続く。まず大野村方式をそれぞれの地域に当てはめて、その中からそれぞれ独自の方式を作っていこうと。津山方式、置戸方式をね。中で特徴があるのは、置戸。産業教育でなく社会教育としてやり、本当の人づくりをしていることね」
―地域づくりは人づくりだと言いますよね。
「そう、たいがいどこでも、地域振興は人づくりだと言いながら、モノを追いかけます。本音は経済振興なんですよ。ところが経済振興に持ってゆく自信のある人が不在だった。まあ頑張れば何とかなるわ!でやったけど、産業として位置づけるとね、すでにある産業と比較しちゃう。たとえば酪農は20億円あるのに工芸はいつまでも3億円にしかならんとか、そんな見込みのないものは最初からするなとかね。そういう問題が出てきた。ところが、酪農は借金地獄ですよ。工芸は借金なしでできます。確かに蔵は建たないけど個人の生活は十分に可能だ。しかも芸術性が高まれば、芸は国境を越えてゆくんです」

今まで説いてきたことを実証したい
―仙台から故郷の大分県・湯布院町(現・由布市)に戻ってこられたのはどうして?
「ここに来たのは平成3年ですが、いわゆる先祖帰りね。53歳、そろそろ身を固めないと、最後まで旅芸人のルンペンで行っちゃうのかなと思ったりして。湯布院町の商工会が木工技術講習会をやって、仙台から何回かここにも通ってきてはいたんですよ。
湯布院町に木工生産の歴史があったわけではない。消費の歴史はありましたが。生産はわたしがきて始めたんです。年間350万の客が来る、温泉と観光の町。100軒ある旅館が、個性あるサービスをしていくためには、個性ある営繕がいるはずなんですね。今までそれを外から買ってきたんだけど。地元に相応しい生産技術がないと観光そのものがやっていけなくなる。そういう背景のからみの中にあって、私がここにいるわけなんですね」
―材料の調達はどうされています?
「木を選ばなければこの辺に転がっていますよ。木材市場で価値のないものでも、工芸の世界では役に立てることができる。ただし、そのためには基本技術を身につけておかないと。ですから、今の林業家が基本的な加工知識を持ってさえいれば、植えて育てる自分の行為を、違う目で見ることも可能になるのね。転がっている無用のものでも有用な資源になりうる可能性があるから。それはすべてワザとの関係でしょ。ワザがあれば笹でも資源に見えてくる。ワザがなければゴミと同じ。特別のものでなくて、目的に合わせて活用するのが技術です。たとえば、椀にならないような柔らかい木はどうすれば固くなるか、黒い木はどうすれば白くなるか。その要件に対応できるのがワザで、ワザは訓練を要します。訓練の積上げが芸なんですよ」
―普通の人で技術を勉強して、いっぱしになるにはどのくらいかかりますか。
「いっぱしはそこにいる(別室で作業中のお弟子さんの女性を指して)。2年です。ほんとは5年と言いたいところだけど、今の人は身が持たない。昔は年季明けまで自分を殺し、権利を主張しないで真剣に芸に励んだものです。今は励むんじゃなく、過ごすんですね。自由で幸せと言えばそうだけど、芸は身に付かない。どうせ身に付かない芸ならね、無理に長くするよりも短くしてお互いに考え直す時間をとったほうがいいんです。最終的には美に対する関心がないといっぱしになれません。せっかく使うなら美しいものにしたい、せっかく作るなら美しいものを作りたいという」
―ここに研究所を構えられて、それまでやってこられた地域振興と関わるお仕事が十分にできなくなったようなことは。
「それはありません。今まで通りやっていきたい。ただし、今まではかっこいいことを言っていればよかったのね。それを今度は自ら実証しなくてはならないわけね。証明できなければ、ホラを言ってきたことになりますから。食べさせてもらえればよかったのが、ここを維持し、皆を食べさせなきゃならなくなった。その違いはありますよ。定住すれば、町づくりの上での役割や義務も果たす、身の上相談にも乗ると。今までの延長線の上に立ってはいても、経営者の立場で、この館を背負ってゆくからには変わらざるを得ない面もあります」

副業分野を充実させる地域デザインの確立を
―昨日、中津江村(大分県日田市)の林業家・田島さんのところでろくろ指導をなさいましたが新規に始めたばかり、これからですね。
「一人だけに技術を教えても意味はない。地域振興にならないのです。みんなが幸せを感じ取れる仕組みにしないとね。そうでないとお金も使えない。大勢が勉強したというなら、村もお金を出せるでしょ。だから田島氏にも隣り近所に声をかけ、やがて村にも話を持っていくようにと言うんです。
80のじいさまが草鞋を作っていて珍しいなんていうのは地域問題ではないんだという視点ですね。マスコミの話題性と、地域問題とは違うのです。これはとってもやっかいで、効果の出にくいものだ。山村の工芸や文化は、真剣に皆が感性を増幅でき、じいさまの技を文化につなぐデザインがないと消えてしまいます。
そこでその辺のことが分かるリーダーが必要となる。一攫千金を追いかける山師のような人に説いてもダメ。田島氏は地域の話も分かる人だからね。それで手を出した。今までは人を選ばないでやってきたけど、今後は選んでみようと。選ぶからには、10日ぐらい掛けて用意し、稽古を積んで初舞台に臨む。それは芸に対する私自身の問題です。林業や農業の現場に自分の芸が通用する芸かどうかはこちらの問題だからね。中津江は田島夫婦の頑張りにかかっている。他のどことも違う中津江物語を作っていけるかどうかが」
―これからなさりたいことは?
「けっきょく文化と経済の融合ね。文化をきちんと支えるためには経済がしっかりしていなくてはならない。地域の中の、とりあえず林業に絞って言うと、森林文化と森林経済というものを、時代時代にあわせて、ふくらませるためにはどうしたらいいか。丸太だけのところから、基本的な加工技術も身につけてみようと。そこから今まで体験しなかった木との関係が見えてくる。日常が安定してないとだめでしょ。ですからかつて副業経済があったように、今の新しい時代に合った副業分野を研究し、主業を守り通す思想を形成しなくてはならない。地域デザインとしてしっかり組み上げて、そこでみんなが経済的に保証しあえる関係をつくる。そこから文化を高めていく。そこが、誇らしい山村のデザインとして、まだ完全に解けていない。これからです」
1997年7月29日、湯布院の工房にて収録。
時松氏の著書は、「低座の椅子と暮らしの道具店」で販売中です。
時松辰夫プロフィール

時松辰夫(ときまつ・たつお)
1937年大分県九重町生まれ。大分県湯布院町在住。アトリエときデザイン研究所代表。家具職人、大分県日田産業工芸試験所を経て、東北工業大学工業意匠学科(現・産業デザイン学科)・第三生産技術研究室の研究員に招聘される。岩手県大野村(現・洋野町)、北海道置戸町をはじめ全国30ヵ所以上で木工ろくろを活用した地域材の活用法やデザインを指導。第12回国井喜多郎産業工芸賞受賞(1984年)、第47回日本クラフト展大賞受賞(2008年)など受賞歴多数。2021年83歳で永眠。