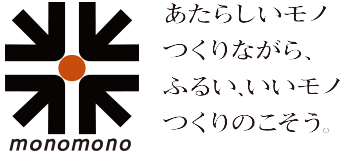ペイントが好きな欧米人、白木を好んだ日本人
「白木(しらき)」というのは、表面に塗料などを塗っていない地のままの木、という意味です。
戦後すぐ、占領軍が上陸して、日本の住宅に住んだことがあります。そのとき、まず日本人がびっくりしたのは、畳の部屋に靴をはいたまま上がってきたことと、床の間から障子の桟までペンキを塗ったことです。ひどい場合は庭石にまでペンキを塗りました。
この住感覚の違いを、日本人は一種の嫌悪感を持ってながめるしかなかったものです。占領軍は日本人にとって「不思議な人たち」でしかなかったのです。
しかし、欧米人にとっては、靴のまま部屋に入るのもあたりまえだし、庭石にペンキを塗るのもあたりまえ。日本人には考えられないことですが、欧米の家の庭には木の柵があり、年中、色の塗り替えをやっているわけですから、その延長で、庭石にも自分の好みの色を塗ったとしても、なんの不思議もないのです。そして、床の間や建具にしても、むこうでは塗ってない建具が少ないくらいで、塗ることが常識なのです。
これは欧米人が悪趣味なのではなく、木の寿命を伸ばし、木が傷まないようにする、彼ら流の生活の知恵からきた習慣だと思うのです。どうせ同じようにペイントするならば、好みの色に塗ろう、ということなのでしょう。
日本人はどうでしょうか。家を建てるのだったら白木。障子なども白木のほうがいい。建具だけではなく、テーブルやお盆などでさえも白木を好みます。この違いは、一口でいうならば、日本人と欧米人の木に対する考え方の違い、風土の違いなのです。
中国では寺院でも色を塗っています。それもどんどん塗りかえています。日本の場合、奈良時代などには中国渡来の様式で色を塗っていたのでしょうが、その後、塗り直しをしていないところがほとんどです。
法隆寺あるいは唐招提寺などの奈良の寺院は、建立されたときは大変美しい色でカラフルに、英語でいえばペイントされていたわけです。五色の色を、柱にも垂木にも、肘木にも塗って、外観も部屋のなかもカラフルでした。それが年とともにはげ落ち、それを日本人はほとんど塗り直さなかったのです。ですから、いま古い寺院はほとんど「白木」の状態です。
なぜ色を塗り直さなかったのか。日本には「白木信仰」があって、白木のものを良しとし、白木のものを崇めるという宗教的な感覚があります。そして即物的に考えても、日本人と木のかかわりは、建物から家具、それからお盆などの器を通じて、いわゆる、「肌の合う」間柄なのです。
木綿と白木。これは人間と「肌の合う」ものです。たとえば夏、風呂上がりに裸で縁側に座ってうちわを使う。なんとも気持ちのいい一瞬ですが、そのときに柱にもたれかかったら、そこにペンキが塗ってあった、となれば、どんな感じをうけるでしょう。きっと気持ち悪いと思うにちがいありません。そういう皮膚感覚を通して「白木」は非常にいい感じだと体験的に理解・評価しているのです。
手で触れても、寄りかかっても、白木の持つ肌ざわりにはやさしさがあります。そういうことが木に色を塗らないことの基本にあると思います。
白木は生きている
そして白木のものは長持ちするという白木信仰に基づく信念を僕らは持っているようです。事実、法隆寺などは千三百年も風雪に耐え、いまだに健在なのです。
法隆寺に使われている 檜の強度を、二つの大学が共同で調査したことがあります。それによると、修理のために加えた部材を含めて法隆寺に使用されている檜の強度テストを行なった結果、法隆寺の建材は、建立されたときと同じ強度を保っていることが判明しました。
もう少し詳しくいうと、檜は、伐ってから百年、二百年と少しずつ強度が増し、千年くらい経つと少しずつ老化が始まり、強度が落ち始めるということで、千三百年経つとほとんど伐ったときと同じ強度に戻るといいます。そうしたことからいうと、法隆寺の場合は、いま建立された時と同じ強度を持っている、ということになります。
ふつうの考えでは、木は伐ったときから老化が始まりそうなものですが、木は、伐っても生きている素材なのです。生物素材は、無気質なものと違い、テーブルになったり、あるいは柱となってからも組織が生きているのです。
木は板などに加工されたあとも、呼吸作用といって、人間が肺で呼吸するのと同じように細胞が呼吸しています。空気中の水分を取りこみ、水分が多すぎると空気中に放出するというH₂O呼吸で組織の生命力を維持しています。そのために、法隆寺の檜のようにある期間中はだんだん強くなっていく、という現象も見られるのです。
ペンキを塗ったら木が窒息し、木の寿命はむしろ縮む、というのが、日本人の「カン」の科学でしょう。法隆寺は塗らなかったために、いままで強度を保持できたのだ、という説もあるくらいです。
こうした法隆寺の科学的データを見るまでもなく、ペンキを塗っていない白木のものは、長年使っているとだんだん色つやがよくなり、漆を塗ったものにくらべ、むしろ美しさを増すということを、日本人は生活のなかで知っていたと思います。
塗りは時間とともにはげ落ちる。たとえば、漆のお椀は、使っているうちにはげてきてみっともなくなる。しかし、何も塗っていない木の器は、色がどんどん良くなって、百年でも二百年でも使えたという事実があります。
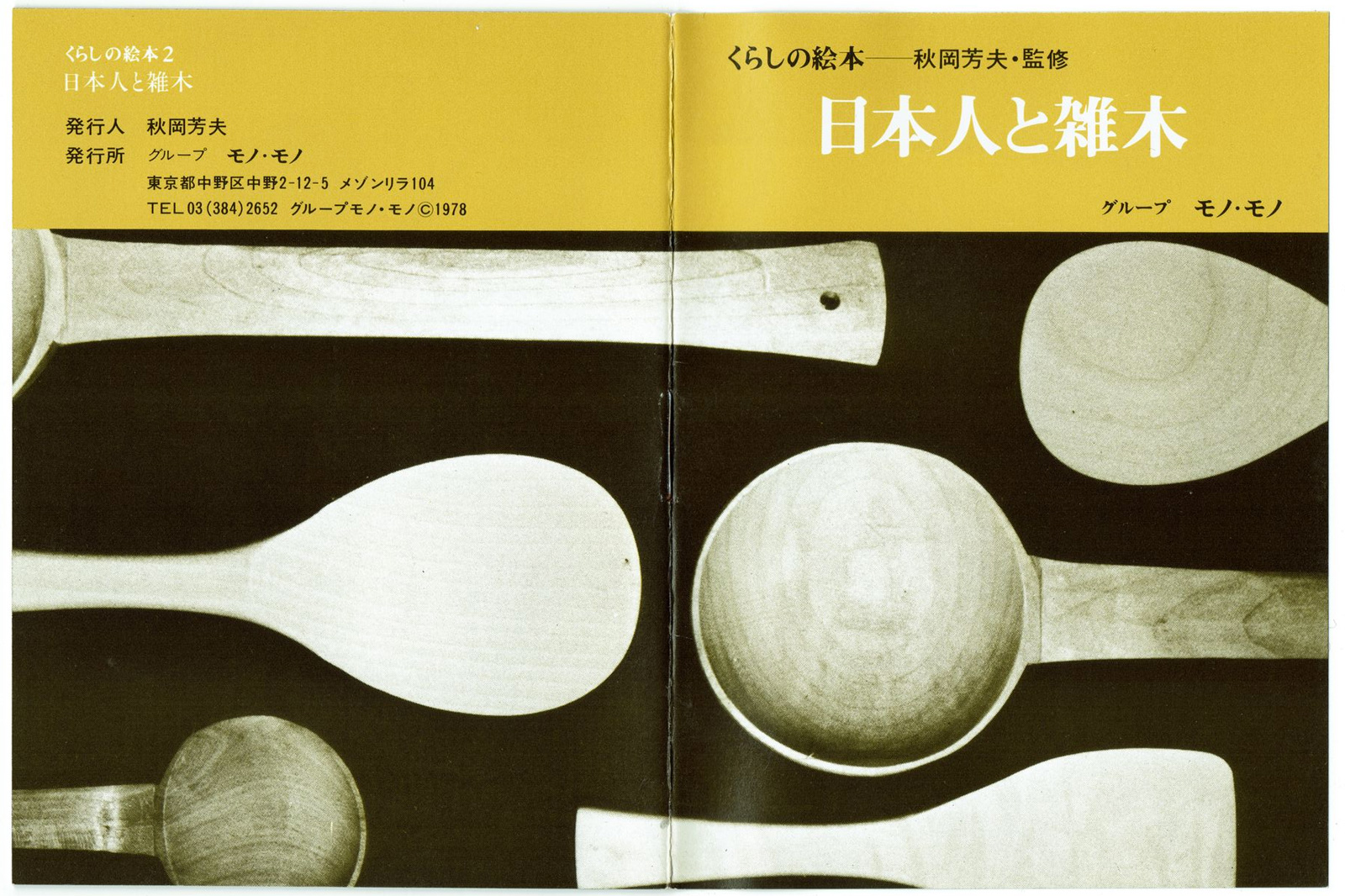
木と人間の生命的共感
白木のものは、ただ長持ちするだけではなく、二百年ぐらい経つと非常に完成した色つやになってくる。法隆寺は千三百年くらいたっても、まだ腐らない。二百年経ったお盆のほうが新品よりきれいだ。
こうした使いこんだ白木のものをきれいだと感じるのは、生きもの同士、木と人間の生命的共感なのです。
木は植物という生きもので、僕らは人間という動物ですが、ともに生きもので、「おまえさんは長生きですごいな、おまえさんは呼吸してるんだよな」 と、生きもの同士の共感のようなものが、人間と白木のものとの間にはあります。
しかし、白木のものは、そのまましまいこんでいたのでは、きれいにはなりません。もう、いまでは死語になっていますが、日本語で「使いこむ」という言葉がありました。それから「拭きこむ」という言葉もありました。
ものの手入れ、掃除の言葉ですが、「廊下を拭きこんでいいつやを出す」といいました。いまは掃除機でスーッとゴミを取るだけになりましたから、拭きこむといっても、なんのことやらわからない若い人も多いと思いますが……。
昔はゴミはほうきで掃き、必ず濡れたぞうきんで拭きました。そのあとで「からぶき」をやりました。からぶきは「拭きこむ」という言葉と関係があります。からぶきすると家が長持ちしてつやがよくなり、寄りかかったり、その上を歩いたときに素肌を喜ばしてくれるという、生活の知恵に裏づけられた生活技術だったのです。
使いこんで拭きこんだものには、ペンキや漆を塗ったものから得られない快感がありました。 こうした白木のものと人間のつき合い方は生活の知恵でもあったし、人間の喜びにもなっていたわけです。
白木は頼りになる相手で、拭いてやると色つやがよくなる。白木は人間と心が通じ合う生きものなのです。
出典元・著作の紹介
『新和風のすすめ』
モノ・モノ | 文庫本 | 2020(復刊)
秋岡芳夫が手がけた最後の著書。自然と共存してきた農山村の暮らしを例に出し、住まいも食事も着るものも、めいめい自分に合うよう工夫して作ったり使ったりする、そういった日々の営みの集積が日本の生活文化の伝統だと説く。元来クリエーティブだった日本人の暮らしをおさらいして、新しい暮らしを考えよう。それが秋岡がとなえる「新和風」。ボーダレスの時代だからこそ読み直したい一冊だ。
こちらの本は「低座の椅子と暮らしの道具店」でご購入できます。
※本ページの掲載記事の無断転用を禁じます。当社は出版社および著作権継承者の許可を得て掲載しています。
※掲載箇所:「新和風のすすめ」 P74-80